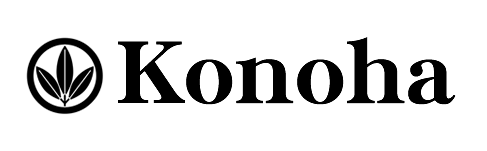山梨県の縄文土器
山梨県で発掘された縄文土器は、その独特な造形と装飾で知られています。以下に、主な土器の種類とその特徴を解説します。
1. 水煙文土器(すいえんもんどき)
水煙文土器は、山梨県で特徴的に見られる土器で、口縁部に水蒸気が立ち上るような曲線的な装飾が施されています。これらの装飾は、まるで水煙が立ち上る様子を表現しているかのようです。
2. 塔状把手土器(とうじょうとってどき)
塔状把手土器は、持ち手が塔のように立ち上がった形状を持つ土器です。持ち手部分が高くそびえ立つことで、視覚的なインパクトを与えています。
3. 深鉢形土器(ふかばちがたどき)
深鉢形土器は、深い鉢状の形を持つ土器で、山梨県内の遺跡から多く出土しています。特に、塩山市上萩原字殿林遺跡から出土した深鉢形土器は、高さ72cmの大型で、曲線文様の美しさが際立っています。
4. 諸磯式土器(もろいそしきどき)
諸磯式土器は、縄文時代中期の土器で、特に諸磯C式土器は、その均整の取れたフォルムと文様の美しさで知られています。山梨県立考古博物館で展示されており、多くの土器愛好家を魅了しています。
5. 異形台付土器(いぎょうだいつきどき)
異形台付土器は、縄文時代後期に見られる特殊な形状の土器です。台座部分が特徴的な形をしており、祭祀的な用途が考えられています。
6. 刻目突帯文土器(きざみめとったいもんどき)
縄文時代前期〜中期にかけて山梨でも出土する、帯状の突帯(盛り上がった部分)に刻み模様が施された土器です。
この装飾は、道具で押し当てることで文様を生み出しており、視覚だけでなく触覚でも楽しめる立体的な装飾が特徴です。
模様の規則性とリズム感が際立っており、まさに「縄文のリズム」が形になったような意匠です。
7. 把手(とって)付き土器
山梨の縄文土器には、持ちやすさや装飾のために「把手(とって)」がついた土器も多く見られます。
特に、動物の顔や抽象的な文様をかたどった把手は、実用性を超えた象徴的な意味を持っていた可能性があります。
これは、器を単なる道具ではなく「意味を持つ造形」として扱っていた証とも言えます。
8. 装飾付きの浅鉢・皿形土器
あまり知られていませんが、山梨では浅鉢や皿のような土器にも、大胆な渦巻文様や曲線装飾が施されているものがあります。
一見シンプルな器にも、精妙なバランス感覚と美意識が込められており、現代のクラフトにも通じる完成度です。
9. 人面・動物面モチーフの装飾土器
土器の一部に人や獣の顔を模した突起が施された、極めてユニークな作品も出土しています。
これらは「見られている」「守られている」といった精神的な意味合いを持っていた可能性があり、
単なる装飾ではなく、器そのものが祭具や守護像としての役割を持っていたと考えられます。
10. 複合型土器(合体・連結型)
山梨では、複数のパーツを組み合わせて一つの土器に仕上げたような複合構造の土器も出土しています。
上下が別素材のように見えるもの、台と器部分のバランスを極端にデフォルメしたものなど、
工芸というより、まるで立体構成アートのような試行錯誤の跡が見られます。
縄文人の「かたちを探る衝動」そのものを感じさせる一群です。
9. 人面把手付土器(じんめんとってつきどき)
持ち手の部分に人の顔を模した造形が施された土器です。把手部分に目・鼻・口のような形を作り出すことで、単なる持ちやすさだけでなく、器に「見守る存在」や「霊的な力」を宿す意図があったと考えられます。祈りや守護の象徴としての器だったのかもしれません。
10. 人体文土器(じんたいもんどき)
一の沢遺跡などから出土したもので、踊る人間の姿を文様として描いた土器。文様が連続して描かれており、物語のように「動き」や「感情」が込められているのが特徴です。祭祀や踊りの場面を器に封じ込めた、記録的・象徴的な意味合いをもつ土器です。
11. 出産を表現した土器
鋳物師屋遺跡などからは、出産の瞬間を模したような土器が出土しています。出産する女性を象った装飾が付けられ、命の誕生や繁栄を祝福する意味が込められていたと考えられます。土器を「神聖な母体」として捉える視点が感じられます。
12. 双口土器(そうこうどき)
口が2つある構造をした異形土器。機能的には使いづらく、儀式や特別な場で使われた祭祀用と見られています。2つの口を持つことで「対」や「循環」を意味していた可能性もあり、精神性の強い意匠とされています。
13. 埋甕(うめがめ)
乳幼児の埋葬に使われたとされる土器で、多くは口を下に向けて地中に埋められていました。器そのものが「命の包み」としての役割を担い、母胎や宇宙の象徴として使われていたと解釈されています。
14. 朱彩土器(しゅさいどき)
表面に赤い顔料(朱)で彩色された土器で、山梨でもいくつか出土しています。色彩が加わることで、視覚的な意味だけでなく、儀式や権威との関わりも想起させます。特別な人や場面に用いられたと考えられます。
15. 釣手土器(つりてどき)
吊るすような把手(つり手)を持つ、香炉形の器。装飾性が高く、内部に火を灯して使用された可能性があります。光と煙が舞う様子を器に取り込んだ、祭祀的な美しさを備えた造形です。
16. 面文土器(めんもんどき)
胴体部分に「顔」を象ったような文様を施した土器。人の顔や目のような文様は、見る者との対話や精神的交信を表現する意図があったとも言われます。祭壇や祈りの場に置かれた可能性があります。
17. 勝坂式土器(かつさかしきどき)
勝坂式は縄文中期の代表的な様式で、山梨では酒呑場遺跡などから出土。重厚で立体的な装飾が特徴で、動物の背骨や蛇を連想させるようなモチーフが多く、造形への強い探究心が感じられます。
18. 立体貼付装飾土器
器の表面に粘土を貼り付けて立体的な模様を作り出す装飾技法。山梨の土器には、ひとつひとつの文様に個性があり、生命感のある動きが与えられているものが多く見られます。
19. 胴部に刻線が施された細型土器
比較的シンプルな形ながら、胴部に繊細な刻線や点描のような模様が施された土器。日常的な器に見えて、細部に美的感覚が宿っており、日常の中に祈りや美を込める縄文人の精神性が垣間見えます。
20. 複合型土器(ふくごうがたどき)
複数のパーツを合体させて制作されたような構成を持つ土器。台と胴体のバランスが極端だったり、把手や突起の数に規則性がなかったりと、機能性よりも“かたち”の可能性を追求したような作品が見られます。
21. 鉢状脚付き土器(はちじょうあしつきどき)
器の下部に脚部が付いた、台座のような構造を持つ土器。高坏のような形状で、祭祀や神前での捧げ物用に使用されたと考えられます。器を地面から浮かせることで「神聖な領域」を演出し、現世と神域を分ける象徴的な構造です。
22. 環状突帯文土器(かんじょうとったいもんどき)
器の胴部に、帯状に突き出た装飾(突帯)が連なるように付けられたもの。突帯の上に細かい刻線や押型文が施される例もあり、触れることで伝わる“指のリズム”が土に刻まれています。視覚と触覚の両方で文様を楽しむ器。
23. 羽状装飾付き土器(うじょうそうしょくつきどき)
翼のような左右対称の装飾が施された土器。風や鳥を象徴していたとも言われ、空を仰ぐ精神性や“飛翔”のイメージを形にしたとも解釈できます。静的な器の中に動的な空気を宿らせる、詩的な造形が魅力です。
24. 小型精緻文土器(こがたせいちもんどき)
手のひらサイズでありながら、極めて緻密な文様がびっしりと彫られた土器。実用品というよりも、祭祀や副葬品、装身具的役割を担っていた可能性もあります。縄文人の“手と目の密度”を感じさせる、密やかな美のかたち。
25. 楕円形口縁の変形土器(だえんけいこうえんのへんけいどき)
口縁部が真円ではなく、楕円や波形に変形したタイプ。成形時の柔らかさを活かした意図的な変形と見られ、視覚的な揺らぎが造形に奥行きを生んでいます。意図的な不均衡=“美しい不安定”を追求した土器とも言えるでしょう。
26. 筒形土器(つつがたどき)
胴が細長く、全体に筒のようなシルエットを持つ土器。山梨県では祭祀関連の遺構から出土する例が多く、液体や供物を納めるための器と考えられています。装飾は比較的控えめだが、均整のとれたプロポーションと口縁部の作り込みに美意識が見て取れます。
27. 三脚土器(さんきゃくどき)
底部に三本の脚(足)を持つ土器。釈迦堂遺跡などからも出土しており、加熱用としての実用性と同時に、脚部の造形が際立つため、特別な場で用いられた可能性も指摘されています。山梨では、脚に装飾を施した例もあり、祭具としての役割が強かったことを伺わせます。
28. 波状口縁土器(はじょうこうえんどき)
口縁が波のようにうねる独特のフォルムを持つ土器。波打つ形は、液体の動きや風、火の揺らぎを象徴したものと考えられ、動きのある造形が特徴です。山梨で出土した波状口縁土器は、深鉢形の中に分類されることが多く、機能と象徴性の両立が見られます。
29. 穴文土器(けつもんどき)
器の表面に小孔(あな)を穿ち、そこに装飾性を見出した土器。押し型や刻線とは異なり、空隙によって模様を生み出す点が特徴。山梨の出土例では、器壁が厚めで装飾的要素としての「穴」が並列配置されており、意匠の一環として計画的に構成されています。
30. 渦巻文土器(うずまきもんどき)
胴部や口縁部に渦巻文が描かれた土器。渦は自然界に多く見られる図像であり、縄文人にとっても特別な象徴だったと推測されます。山梨県内では、重厚な深鉢形に大胆な渦巻文を施した土器が複数発見されており、造形と精神性が高いレベルで融合しています。
山梨県で縄文土器を鑑賞出来る博物館や展示場
1. 山梨県立考古博物館
• 甲府盆地南部の「甲斐風土記の丘・曽根丘陵公園」内に位置し、旧石器時代から明治時代までの考古資料約1,500点を常設展示しています。特に、国の重要文化財に指定された縄文土器のコレクションは見応えがあります。
2. 釈迦堂遺跡博物館
• 釈迦堂遺跡から出土した多数の土偶や高い芸術性を持つ土器を展示しています。出土品5,599点が国の重要文化財に指定されており、そのうち土偶は1,116点に及びます。
3. 山梨県立美術館
• 2022年に開催された「縄文―JOMON―展」では、県内各所に所蔵されている代表的な土器や土偶を一堂に展示し、縄文文化の美術的価値を紹介しました。
4. ふるさと文化伝承館(南アルプス市)
• 2階展示室にて、国指定重要文化財「鋳物師屋遺跡出土品」205点を全て展示しています。また、北原C遺跡の水煙把手式土器など、市内出土の縄文資料の優品を鑑賞できます。
5. 北杜市考古資料館
• 市内で出土した旧石器時代から中世までの出土品を展示。津金御所前遺跡で出土した出産文土器も常設展示されています(貸出期間中は複製品を展示)。
6. 甲府市藤村記念館
• 甲府市内の歴史的建造物で、特別展示として縄文土器を公開することがあります。
7. 韮崎市民俗資料館
• 韮崎市内の遺跡から出土した縄文土器や石器を展示し、地域の歴史を紹介しています。
8. 都留市博物館(ミュージアム都留)
• 都留市周辺の縄文遺跡からの出土品を展示し、縄文時代の生活様式を学べます。
9. 富士吉田市歴史民俗博物館
• 富士北麓地域の縄文遺跡からの出土品を展示し、富士山周辺の先史時代の文化を紹介しています。
10. 笛吹市石和歴史民俗資料館
• 笛吹市内の縄文遺跡からの出土品を展示し、地域の歴史と文化を伝えています。
11. 上野原市郷土資料館
• 上野原市内の遺跡から出土した縄文土器や石器を展示し、地域の先史時代の文化を紹介しています。
12. 甲州市勝沼ぶどうの丘資料館
• 勝沼地域の歴史を紹介する中で、縄文時代の出土品も展示しています。
13. 大月市郷土資料館
• 大月市内の縄文遺跡からの出土品を展示し、地域の歴史を学ぶことができます。
14. 南部町立南部博物館
• 南部町周辺の縄文遺跡からの出土品を展示し、地域の先史時代の文化を紹介しています。
15. 身延町郷土資料館
• 身延町内の遺跡から出土した縄文土器や石器を展示し、地域の歴史を伝えています。
16. 早川町歴史民俗資料館
• 早川町周辺の縄文遺跡からの出土品を展示し、地域の先史文化を紹介しています。
17. 昭和町歴史民俗資料館
• 昭和町内の遺跡から出土した縄文土器などを展示し、地域の歴史を学べます。
18. 市川三郷町歴史民俗資料館
• 市川三郷町周辺の縄文遺跡からの出土品を展示し、地域の文化を紹介しています。
19. 甲斐市双葉ふるさと歴史館
• 甲斐市内の遺跡から出土した縄文土器や石器を展示し、地域の歴史を伝えています。
20. 中央市豊富郷土資料館
• 中央市周辺の縄文遺跡からの出土品を展示し、地域の先史時代の文化を紹介しています。